- 2024.09.03
- 着付を通して日本文化を学んでみませんか? 10月生徒募集中
こんにちは、きもの伝承会サポートスタッフの折笠です。
今回は10月開講予定のいわきで開催される着付け教室を紹介します。
いわきの着付け教室は平駅前のラトブ2F(着物のふく屋内)にあります。
昨年4月に開講いたしました。
きもの屋の中で着付けが出来るの?って不思議に思う事もあるかもしれませんが実はふく屋ラトブ店の店内に16畳の和室が設置されているのです。そこで着付けを習うことが出来ます。
また常磐の着付け教室もふく屋本店内にございます。
こちらはもともと和室がございますので問題なく着付け教室が出来る運びとなっております。
4月より心機一転スタート致します。
1回1000円のレッスン、ベテランの講師の先生、着物と帯が無料ですので手ぶらで通えるところが魅力です。
教室は感染防止としっかりと覚えてもらえるよう先生の目が届く範囲で質の高い授業を目指し少人数制をさせて頂いております。
受講時間は二時間、午前コース(10:00~12:00) 午後コース(13:30~15:30) 夜間コース(18:30~20:30)となっております。
12回の長くもなく短くもない丁度良い受講期間となっております。教室自体がアットホームな感じですので多少の遅刻もOKです。
春からなにか習い事を始めてみようと思っている方、是非、日本人の素敵な習い事をやってみませんか(^^)
因みに受講する年代は20代から70代まで幅広いです。世代間を超えた仲間づくりが出来ます。
- 2024.07.24
- 浴衣姿でランチ会^_^

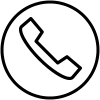
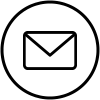



10月7日からいよいよ着付け教室が始まります☆
こちらの着付教室は文字通り「初めての着付け教室」なので、襦袢に半襟を付けるところから着物を着るときに必要な小物の事やその歴史も学べます。
基礎からのレッスンですので未経験者大歓迎!まだまだお申し込み受付中です(*'▽'*)
現在受講中の方々も20代のお仕事をしている方から、70代のゆっくり趣味を堪能したいという方まで年齢層も幅広く、ベテランの講師が丁寧に教える着付け教室です٩( 'ω' )و!
初歩から始める着付け教室は12回のカリキュラムがあり、それに沿って授業が進んでいくため開講すると途中からの入会が難しくなってしまいます。
迷っている方もまずお申し込みくださり、そのうえで判断していただいても大丈夫です。
見学のご希望も随時承っております♪どのような雰囲気か見にぜひ一度覗いてみてください・:*+.\(( °ω° ))/.:+
毎年3月と9月に募集を開始し4月と10月に授業が始まります。着物貸出無料、1回1,000円のレッスン料で気軽に始められます。
1教室4名以下の少人数制ですので、一人ひとりその人に合った着付けスタイルに寄り沿い丁寧に指導いたします。
今年こそ着物を着たいと思っている方→今がその時です!!
詳しく内容などもご案内できますので、いつでもお気軽にお問い合わせください(^.^)/~~~